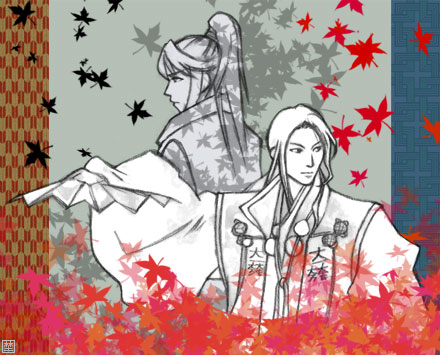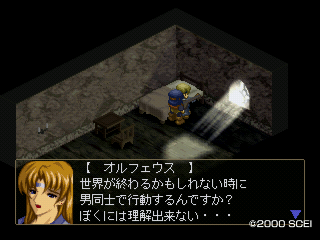TOHOシネマズ渋谷にて、「霧矢大夢ラストデイ」中継に参加。
これは、東京宝塚劇場で上演する月組「エドワード八世/Misty Station」千秋楽、およびサヨナラショーを生中継したライブビューイングです。
涙もあったけれど、最後はからっと明るい、笑顔が弾けるサヨナラでした。
カーテンコールがなかなか止まず、13:30から公演が始まって終わったのは18:30過ぎ。
中継は「タカラヅカスペシャル」以来ですが、あの時よりもアップが多い印象で、もう少し全体の動きが観たいなぁとストレスが溜まりました。もっとも、観客は生舞台を1度見ている方がほとんどだと思いますので、普通は問題ないのでしょう。
映像は販売DVDより美麗な気がします。芝居中、広場で別れを告げるウォリスの瞳から涙が流れたのがくっきり観えました。
後は、音が前方から大音量で放たれるため、劇場の客席から舞台へ向けられている拍手のシャワーを、まるで私が浴びているような、不思議な感覚が残りました。
土日の公演チケットが取れなかったため、この千秋楽中継が初観劇です。
劇評を見聞きして臨みましたので、芝居はスムーズに入り込めましたが、ウォリスの別れと退位の間で時間軸が飛ぶのが惜しいように思いました。ソ連側の画策が劇中で見えなかったのも、話を広げただけで終わった感。
とは言え、大野先生らしいウィットある会話劇で笑いも涙もあり、イギリス紳士・霧矢とアメリカ女性・蒼乃という描き方が、2人のキャラクターに合っていて、素敵な退団公演でした。
ショーは、アニメを流す演出や「魂のルフラン」など、オタクとしてはなんだか座りが悪くて思わず笑うしかない箇所が印象に残っていますが、霧矢・蒼乃コンビによるシーンが極めて少ない不満を除けば、キャッチーな主題歌は好きだし、色々盛り沢山で面白いショーでした。
なにより、両作品がお互いの作品を巧く組み込みあっていたため、芝居とショーで演出家同士が好き勝手してるいつもの2本立てに比べると、1つの舞台として調和がとれていて良かったと思います。
サヨナラショーは、霧矢氏の響き渡る歌声を浴びる至福の時でした。
トップ時代の曲で纏めるのかと思いきや、伝説の新人公演「ノバボサノバ」から「シナーマン」が聞けたのは、本当に嬉しい驚きでした。
ただ、サヨナラショーの場合、知らない公演の曲だと集中力が落ちるものですね。もっと月組公演を観ておくべきだったと思いました。
経歴紹介が長くて、もう少し簡潔にして欲しいと思いました。越乃リュウ組長が持参した原稿の分厚さに、覚悟はしていたのですが、ちょっと長過ぎます。きっと、組長は生真面目過ぎて端折って喋るなんてできない人なのでしょうね……。でも、せめて背景で流れるダイジェスト映像が終わったら、退団者からのメッセージに移るくらいの纏め方を期待したいです。
以下、書き残しておきたいキャストについてだけ。
ヨーク公アルバート(ジョージ6世)@一色瑠加が、美味しい役を上手に消化。2番手役にしておけば退団公演らしい引き継ぎ演出になったのに、と思うけれど、彼の芸暦の最後に相応しい役だったので文句はありません。
その他の退団者では、青樹泉が透明なスターオーラを放っていて、終始格好良かったです。沢希理寿の歌の心地好さは、本当に惜しいと思いました。
チャーチル@一樹千尋は、さすがの巧さ。ただ、ショーにも出演されているとは思わぬ誤算で、「デイドリーム」の歌にはちょっと仰け反りました。ご免なさい。